|
インド・ニューデリーのジャワーハルラール・ネルー大にて国際関係を学んでいた留学生の記録。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
最近の食糧5
(1)スーパー・ドライ ちょっと高めのレストランやバーに行けば、日本製ビールが置いてあることも珍しくない。とりわけよく見かけるのは、このスーパー・ドライ。メニューには、"Asahi"と書かれていることが多い。 だが、酒屋で初めて発見したのは、昨年11月末ごろ、サフダルジャン・ディヴェロップメント・エリア(Safdarjung Development Area)の酒屋であった。ワインを物色していたのだが、店主はこちらが日本人とわかるやいなや(会話の中で)、このスーパー・ドライを奨めてきた。奨められるがままに(むしろ喜んで)購入を申し出たが、なんと品切れであった。先日久々にその店を訪れた時には在庫が豊富にあり、しかも冷えていた。ついに念願かない、購入できた。 小瓶(330 ml)1本でRs. 110。普段自室で愛飲している国内産ビールのフォスター(Foster)が大瓶(650 ml)でRs. 40であることからすると、かなり割高。それでも味がよければ文句はないが、今回購入したものはいまいち。中身がつめかえられているとは思わないのだが・・・、何やら水っぽい。輸入する過程で、時間経過や温度変化のために変性してしまっているのだろうか・・・。残念な味であった。 (2)麻婆豆腐 AjinomotoのCookDo「四川式麻婆豆腐」を利用して作った。豚ひき肉、豆腐、長ネギは自力調達。ほぼレシピ通りに作っているので、もちろん無難に仕上がる。 味はそれなりにいい。が、コストが・・・。これなら近くの日本料理屋Tamuraで注文したほうが割安かも・・・。 (3)さくら 『地球の歩き方』にも掲載されているデリーの超有名日本料理レストラン、さくら。今回、初めて訪れた。日曜日のランチはビュッフェ形式になっている。食べ放題、飲み放題でRs. 1,800(税、サーヴィス料別)。 鮨、天ぷら、焼き魚、煮物、カツカレー、蕎麦、ラーメン、サラダ、デザートなど・・・。飲み物は、ビール、ワイン、シャンパンなど・・・。大満足の品揃え。クオリティも文句なし。それぞれの料理の専門店のレベルには及ばないが(たとえば、日本の天ぷら専門店の天ぷらと比較するのは酷)、価格を考慮しても、十分満足できるレベル。 ぜひまた訪れたい。 (4)Olive Beach 大使館が軒を連ねるチャーナキャプリー(Chanakyapuri)の北にあるホテル、ディプロマット(Diplomat)内のレストラン、オリーブ・ビーチ(Olive Beach)。もちろん高級店の部類に入る。 連れてきてくれた人曰く、「どのメニューもおいしい」とのこと。今回は、サラダ、ピザ、ハム・ソーセージ類の盛り合わせ、パスタを食した。ワインはおなじみ、インド産のスーラ(Sula)。どれも文句なし。ちゃんとしたイタリアン。締めのコーヒーもよかった。 デリーでイタリアンというと、茹ですぎのスパゲッティという印象が強く、こういう高級店でどのようなスパゲッティが出るのか期待していたが、今回はそこにたどりつく前に十分食べてしまい(よくある展開だが)、味わえなかった。機会があれば、次回チャレンジしたい。 PR
先日、ハウズ・カース・ヴィレッジ(Hauz Khas Village)の中級レストラン、パーク・バルッチ・レストラン(Park Balluchi Restaurant)を訪れた。ディア・パーク(Deer Park)という公園内にある。ちょっと派手な内装は高級感を演出しているのだろうが、センスが悪い。外国人客が多かった。
メニューにオクラ炒めを発見(メニュー名は忘れた)。この手の少し値の張るレストランではあまり見かけない。自作時の参考にすべく、注文してみた。 油は多いが、さっぱりとした味付けで、ちょっと拍子抜け。この手のレストランならではのアレンジを期待していたが、安い食堂でも出てきそうな感じだ。無難なオクラ炒め。同行者曰く、「上品な味」。そうとも言える。味付けの方向性は、レシピを参考に自分で作ったものとほとんど同じ。スパイスはおそらくガラム・マサーラー。ただし、違いはオクラの火の通り方。オクラがしっとりとしており、その結果として、調味料がうまく絡んでいる。 これを参考に、自分で再度挑戦してみた。 蓋をして蒸すという工程を入れることによって、しっとりとした食感を得た。代償として素材本来の食感は失われるが、味をしっかりのせることができるので、こちらの調理法の方が、自分の好みに合う。 レストランでの味に近いものを再現できるようになったが、そもそも地味な料理で、インパクトに欠ける。機会があれば、次は何かオリジナルな手法にチャレンジしてみたい。
デリーの観光スポットの1つ、ジャンタル・マンタル(Jantar Mantar)。日曜の午後、近くで用事があったついでに訪れた。ジャイプルのジャンタル・マンタルは訪れたことがあるが、デリーのはこれが初。
入場料は外国人Rs. 100、インド人Rs. 5。もちろんRs. 100払った。 ジャイプルのそれに比べてスケールは小さく、構造物それ自体には興味をそそられなかった。。ただ、人の多さに感心した。外国人観光客は、見た限り皆無であった(自分を除く)。地元の人々、あるいは地方から来たインドの人々で賑わっていた。Wikipediaの記事に掲載されている写真を見ると、ほとんど人が写っていない。今回の賑わいは、日曜午後ゆえの状況だったのかもしれない。 [以下写真のみ]
靴下をいかにしてまかなうか、それが問題だ。
先の記事にて言及したように、通常洗濯を自分で行うことはない。下着類はドービーに、それ以外はドライ・クリーニングを利用する。しかし、この体制でカバーできない部分がある。それが小物類であり、具体的には靴下が問題となる。寮のドービーは靴下やハンド・タオルといった小物を引き受けてくれない。ドライ・クリーニング店で確認したことはないが、おそらく返事は同じだろう。また、仮に引き受けてくれるとしても、コストが見合いそうもない。では、どうするか。諦めて自分で洗濯するか、それとも・・・。 夏の間は、幸いにして、この問題が具現化することはなかった。理由は単純。靴を履かないからだ。素足にサンダル。それで充分。学校生活において、そのスタイルで通せないような局面には遭遇しなかった。多少身だしなみを整えたい場面で、上にジャケットを羽織っていても、足元は素足にサンダル。何ら問題なし。 旅行に出かけるある朝、靴を履いて歩きはじめたとき、靴を履いて歩くという行為が新鮮に感じられた。おそらく1か月以上、靴を履いていなかったのだ。自分の歩き方に違和感を感じるという、不思議な体験であった。 季節は移りゆき、冬。寒い。裸足にサンダルは無理。素足・サンダルのスタイルを維持して生活する人々も少なからずいたが、自分には耐えがたかった。毎日、靴と靴下を履かざるを得ない。夏の間にたまに履く靴下をたまに洗うことくらいは我慢しえたが、毎日靴下を履き、毎日、ないし2~3日に1回という頻度で靴下を手洗いすることは、自分にとって許容できそうもなかった。 洗濯するしかないだろう、とは思わなかった。というのも、もう1つの選択肢が自分の思索の中で説得力を強めつつあったからだ。その選択肢とは、「使い捨て」だ。 現行の社会規範が許容しないであろうことくらいはわかる。環境問題の観点から見ても、この策が倫理的に劣ることは間違いない。しかし、経済的合理性は明らかに使い捨て策を支持していた。近くのスーパーでは、靴下を1足Rs. 20未満で買える。許容しうるコストだ。1足の靴下を手洗いするためにかかる手間を、Rs. 20で省略することができるのであれば、買ってしまった方がいい。そう思った。 この問題への正解はない。そもそも、この問題に限らず、絶対的な正義、あるいは絶対的な悪など存在しないというのが、自分の考えである。有限資源の有効活用という観点からすれば、洗って使いまわすことが「正しい」。自分の留学生活という限られた時間を有効利用するという観点からすれば、使い捨てが「正しい」。 要するに問題は、どちらの観点を重視するかだ。 そして、自分の下した結論は・・・ 結局、洗った。 それも大量に。15足以上。加えてハンド・タオルも。 使い捨てという策に踏み切るべきだという結論に固まりつつあったが、心情的に、捨てることができなかった。「もったいない」精神とでもいうべきだろうか。結局、捨てるでもなく、どんどん買い足した結果、使用済み靴下が山積することとなった。そこで、ふと思った。まとめて洗えば手間は省ける。15足をまとめて洗えば、月2回の洗濯で済む。 合理性と心情の折衷策であった。最終的に、どちらの観点から見ても目的にそぐわない結果となっているような気もするが、まあいいとしよう。靴下の季節ももうすぐ終わりだ。
最近の食糧4
(1)味噌リゾット 学外に居を構える今もほぼ毎日寮を訪れているが、めっきり寮の食堂で食事をする機会はなくなった。留学当初は低い期待値からか、不満を感じることはほとんどなかった。しかし現在は、いろいろと選択肢もある中で、あえて寮で食事を取ろうとは思わない。その理由は、炭水化物にある。 どういうことかというと、主食であるご飯とチャパティーに難があり、食べる気になれないのだ。白米とチャパティーは、昼食と夕食ではほぼ毎回供される(唯一の例外は炊き込みご飯の時)。 チャパティーは、単純に、硬い。相対的に高級品とされるナーンが発酵を経てやわらかくなっているのに比べ、チャパティーは硬い。パリッとした硬さではなく、地味に硬い。焼きたてならまだ我慢できるが、少しでも時間が経ってしまうと、厳しい。留学当初のごく初期は興味本位から食していたが、早々に手を伸ばすことがなくなった。 そうなると白米を主食とするほかなかったのだが、この白米の臭いが次第に気になってしまい、食が進まなくなった。日本米でも炊きあがりには特有のにおいがする。改めて考えてみると、あのにおいを「いい匂い」と感じるか、「いやな臭い」と感じるかはその人の文化的背景に依るところが少なくないのだろう。インドのご飯のにおいは、日本米のそれよりもやや強く、クセがある。経験のない人に説明するのは難しい。米本来の臭いであり、悪いものではないのだろうが、一度気になってしまうとダメなのだ。実際には汁物と混ぜて食べるので、食べられないことはないのだが。 この問題は、自炊をしばしばするようになった今も変わらない。近くのスーパーでちょっと高めの米を買ってきて炊いてみたが、臭いは相変わらずであった。 そこで、ご飯を炊く際には一工夫することが多くなった。今回の写真は、見た目にはほとんどわからないが、味噌と醤油を加えてリゾット風に炊きあげたもの。「リゾット」と呼ぶに値するかどうかはわからないが(たぶん厳密に言えば違う)。ともかく、こうすると臭いは気になりにくい。今度は、香辛料を使ってみたい。リゾットという観点で言えば、パニールも合うかもしれない。 (2)とんこつラーメン やまやの「本格博多長浜生ラーメン」。おすそわけ品。感謝。蕎麦用に購入した湯切り網が役立った。 (3)ビンディー・サブジ レシピ本を参考に(あくまで参考)、玉ねぎとオクラの炒め物に再挑戦。格安食材メニュー。 植物油にクミン・シードを加えて熱し、玉ねぎを炒める。オクラ(ビンディー)、フレーク状の赤唐辛子、塩コショウを加えてさらに炒める。ガラム・マサーラーを加えて混ぜ合わせて完成。 レシピ本に基づいただけあって、味はいい感じなのだが・・・。オクラがうまく味をまとってくれない。味をしっかりのせるには、しっとり仕上げる調理法のほうがいいのかもしれない。ちなみに、玉ねぎを毎度長めに炒めているのは好みの問題。
「北インドの冬は1月26日のレパブリック・デーで終わる」
はぐれ雲さんのブログ「さまよえる団塊世代」の一節。 確かに。そう思った。最高気温も25℃近くまで上がってきたが、昼間は晴れることが多くなり、実際の気温以上に暖かく感じられる。この冬活躍したダウン・ジャケットをクリーニングに出して収納してしまおうか、そんなことを今日は考えていた。 ちなみに、ドライ・クリーニングはJNU内でも利用可能だが、やや割高。たとえば、トレーナー1枚でRs. 30。安物ならRs. 100で買えるものをRs. 30で洗うことには少しためらいを感じる。寮付きのドービー(洗濯専門の職業の人)に頼めばRs. 6で済むが、生地の傷みや色落ちなど難点が多い。それでも安価かつ便利なので、下着等についてはドービーを利用している。寮に住む学生はドービーすら利用せず、自分で手洗いをしている人が多い。話を聞く限り、コストの問題よりも、ドービーのサーヴィスに難があることが理由のようだ。 閑話休題。朝晩は相変わらず寒い。ここ数日は最低気温が10℃以上であったが、予報をみると今週はまだ最低気温ひと桁の日が続きそうだ。 寒さと大気汚染に苦しめられた冬が終わるのは喜ばしいが、4月には早くも酷暑期が待ち構えている。ホーリーまで続くという「束の間の春」を楽しみたい。
今日は祝日、共和国記念日(Republic Day)のため授業は休み。
1月26日は憲法を採択して共和国に移行した日(1950年)。独立記念日(8月15日)とは別もの。重要度の高い祝日の1つ。例年コンノート・プレイスでは軍のパレードがある。60回目となる節目の共和国記念日の今日は、さぞかし大規模なパレードが行われたのであろう。 この日は、JNUでは別の意味を持つ。外国人留学生を中心に、それぞれの出身地域の料理の出店を並べるフード・フェスティバルが行われる。午後6時にスタートしたフェスティバルを訪れると、大変な賑わいとなっていた。25の国や地域の出店が軒を連ねていた。インドネシア、イラク、ドイツの料理を味わった。他には、韓国、ヴェトナム、チベット、ネパール、パレスティナ、フランス、などなどの出店があった。残念ながら今回日本の出店はなし。 見てのとおりの大盛況。祝日のため、寮の食事が出ないということも影響していると思われる。 併せて、移動遊園地的な遊具も出現していた。 左はメリーゴーラウンド的なもの。右は船が振り子状に動く遊具。遊園地で(たぶん)良くあるもの。周囲に十分な安全対策は施されていない。ぶつかってけがをしたら自分が悪いということになるのだろう。 これは小型の観覧車らしきもの。むき出しの座席が設置され、客が座る。動力は人。中心部にいる2人が動かす。 日本の遊園地と比べて、悲鳴がどことなくリアルな気がした。
Sanjoy Bagchi, The Changing Face of Bureaucracy: Fifty Years of the IAS, New Delhi: Rupa, 2007. 592 pg. Rs. 795.
 表紙のイラストが何ともキュートだが、それにつられて買ったわけではない。 インド行政職(Indian Administrative Service: IAS)に長年勤めた著者が、IASの歴史と制度を解説する大著。著者Sanjoy Bagchiは1953年にIAS入りし、マディヤ・プラディーシュ州でキャリアをスタートさせ、通商・産業部門に勤務、1978年から11年間はGATTにアドヴァイザーとして参加、その後もジュネーヴで国際機関に参与したのち、インドに帰国した人物。 The Hindu紙による著者へのインタビュー記事を読むと、「今どきの若者は・・・」的な嘆き節も聞かれる。執筆の意図はそのようなところにあるのかもしれないが、本書自体はそのような領域に止まらず、IASを知る上で非常に有意義な本に仕上がっている。IASに連なる歴史(東インド会社、イギリス統治下のICSなど)から説き起こし、IASの制度と変化を詳説する。とにかくinformative(情報量が多い)。たとえば、給与体系も紹介されている(251ページ)。 IASの基本情報については「インドチャネル」を参照。 Vithal Rajanによる書評。
Food of the World India: The Food and the Lifestyle, Parragon (UK), 2004. 256 pg. Rs. 595.
ついに買ってしまったインド料理のレシピ本。Rs. 595のところをRs. 395に割引されていたため(売れ残り)手に取ったところ、きれいな写真につられて、ついつい購入。パニール・ブジヤー(Paneer Bhujiya)のレシピを調べるために料理本コーナーに行ったのに、購入したこの本にはパニール・ブジヤーは掲載されていない。 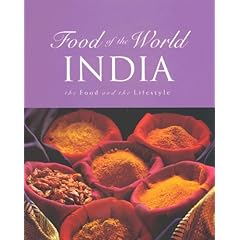 初めにインド料理の歴史や文化の説明。そのあと、各料理のレシピ。写真に大きなスペースを割いているので、紹介されるメニューの数は少ない。100弱。だが、外国人向けと思われるだけあって、基本中の基本をしっかりカヴァーしてくれているのはありがたい。ナーンやドーサ、マサラ・チャーイなど、当たり前の基本メニューまで掲載されている。ベジ料理とノンベジが半々くらい(つまり、ノンベジの比率が実勢よりも高い)のも、外国人向けというところからきているのだろう。 せっかくなので、いろいろなレシピに挑戦してみたいと思う。暇な時があれば。
インターネット事情にまつわる個人的体験談。
(1)ワイヤレス端末 インド到着後の生活環境構築において、マットレス等の最低限の生活物資の調達の次に取り組んだ課題が、インターネット接続回線の開設であった。当初は学内の寮の二人部屋に住んだが、他の寮の一人部屋に移動、もしくは学外に部屋を調達するまでの仮住まいとの位置づけであったため、有線回線ではなく、ワイヤレス端末の利用を模索した。 寮は学内周縁部に位置し、ジャングルも近く、通信状況が悪い。そこで、比較的ましと言われるAirtelの端末を利用することにした。他には、Vodafoneやリライアンスなど、他の携帯電話業者も同様の端末を提供している。 サウス・エクステンション(South Extention)にあるAirtelのオフィスで購入手続き。携帯電話の契約時と同様、住所証明、パスポートなどの書類や顔写真が要求された。端末にはカード方式(data card)とUSBモデムの2種類がある。手軽なUSBモデムを迷わず選んだ(右写真)。端末価格はRs. 3000ほど。このほかに、月額の利用料がかかる。一定のデータ量まで定額で利用できるプラン(超過分は追加料金)と、無制限のプランがあったので、無制限を選択。税別でRs. 999。通信速度はいずれも最大64KB/sとの説明であった。 かくして、インターネット接続を手に入れた。実際に利用を開始すると、そのパフォーマンスはまさに衝撃。遅い。遅すぎる。データ転送速度は1KB/s前後でうろうろ。しばしば0に。テキストだけのメール受信も一苦労。「ナロー・バンド(narrow band)」どころではない。あまりの遅さにストレスを感じるため、精神衛生上も好ましくない。 また、暑い時期はモデムが過熱することも問題であった。 しばらく使っていると、触れないほど熱くなる。冬の現在はそのようなことはないが。 VodafoneのUSBモデムを購入した知人は1か月もたたずに解約していた。もちろん理由は接続速度の遅さである。あまりの遅さに最初は故障を疑ったらしい。 自分のケースでは、遅さの一因は場所にあった。寮の部屋は日本式で言う1階にあるが、3階にある友人の部屋で使ったときは、5KB/s前後を示していた。また、現在住むムニールカー村の部屋でも、もう少し速度が出る。瞬間最大風速的に10KB/s付近を記録することもあるが、それでも基本は一桁。しばしば0になるのも相変わらず。 寮にいる間は使い続けていたが、ネット接続の遅さおよび不安定さが悩みの種であった。ムニールカー村への移動後は、まっさきに有線接続の契約をした(後述)。とはいえ、ワイヤレスがまったく使えないとは言えない。メールの送受信だけと割り切れば、なんとかなるだろう。停電に左右されないと言う利点もある。自分も、予備および外出時用に契約を続けている。税込で月額約Rs. 1,100と、決して安くはなく、支払いに足を運ぶのも大いに煩わしいが、緊急時にネットが使えないという事態を避けるための保険料と考えている。 (2)有線「ブロードバンド」接続 ムニールカー村への移動後、有線のネット接続環境を構築した。ここではAirnetという業者が独占的にサーヴィスを提供している。同じアパートに住む知人はAirtelに問い合わせたが、Airnetの独占地域ということで断られたらしい。ちなみに、JNUの自分がいた寮の有線接続もこの業者である。 業者に電話をすると、その日のうちに部屋にスタッフが来た(郵便すら届かないところなのに、一発で来た)。アパートの屋上の既存の設備からLANケーブルを部屋まで垂らし、窓からケーブルを引く。自分のPCに接続し、設定をして、準備完了。料金プランは接続速度に応じ、64KB/sなら月Rs. 600、128KB/sならRs. 900(もう1つ下があったかもしれない)。接続速度の遅さがトラウマとなりつつあったこともあり、迷わず後者を選択した。 パフォーマンスは上々。最低でも20KB/s、調子のいいときは60KB/sくらい出ている。業者は「ブロードバンド(broad band)」を謳っているが、日本の感覚ではとてもそうは言えない。接続がダウンすることもさほど多くない(当初は全くと言っていいほどなかったが、年末以降はときどきダウンする)。ただし、停電時はアウト。 月々の料金の支払いに電話で業者を呼ばなければならない(そうしないと接続を止められる)という厄介もあるが、現在のサーヴィスには基本的に満足している。事前に超ナローバンドに馴らされていたためもあるだろうが、メールやネット閲覧を中心とした現在の利用に必要な接続速度は確保されている。 もちろん、Airtelは最大2MB/sのサーヴィスを提供しているらしい、などと聞けば、うらやましく思う。 (3)その他 以上は、個人での契約の話。JNUの学生で、このように個人でネット接続環境を持っているのはおそらく少数派と思われる。そもそもPCを持ってない学生も少なくない。 学内には各スクールや図書館にネット利用可能なPCが設置されている。自分のスクールでは、10台ほどが設置されているが、作動するのはうち4台ほど、ちゃんとネット接続ができるのは2台くらい。いずれもウィルス感染と思しき症状が見られる。図書館は30台ほどあり、こちらはメンテナンスが行われているので多くが使える状態にある。その多くがWindowsではなくLinuxを採用しているため、ウィルス感染も比較的ましな状況にある。 こういった備品のPCの他には、サイバーカフェを利用する手がある。学内にもあるし、街に出れば多くある。安いところならば、1時間Rs. 15くらいで利用できる。寮にいたころは、学外のサイバーカフェに足を運ぶ機会も多かった。 なお、学内にワイヤレス接続システム(Wi-fi)を整備するという噂がある。JNUの設備投資は「遅々として進んでいる」という印象なので、 いつになるかはわからないが、いずれは実現されるだろう。 |
プロフィール
HN:
toshi
性別:
男性
自己紹介:
2008年7月から2010年5月まで、ジャワ―ハルラール・ネルー大学留学。
最新記事
(07/24)
(07/22)
(07/19)
(07/19)
(07/18)
(07/17)
(07/16)
(07/12)
(07/12)
(07/11)
本棚
カレンダー
アーカイブ
ブログ内検索
カウンター
|



