|
インド・ニューデリーのジャワーハルラール・ネルー大にて国際関係を学んでいた留学生の記録。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今月中旬、JNU内のブラフマプトラ・ホステル(寮)へと引っ越した。
2年目に突入し、いよいよ佳境を迎えつつある留学生活だが、これまでを振り返ると、研究活動以上に、衣・食・住への苦労が思いおこされる。寮の個室という安住の地を手に入れた今は、それらの苦労からかなりの程度解放され、研究により多くの時間を割くことが可能になった。しかし、そこに至るまでの道のりは長く険しいものであった。 インターネット環境の構築が完了し、一連の引っ越し作業を終えた今日、これまでを書き出してみることとする。 ここに語られるのは、1年以上にわたる、ある引っ越しの記録・・・。(長文) PR
ここ数日、雨がよく降る。
おかげで涼しい。
引っ越し中。
新居はインターネットの敷設がまだなので、とても不便。
アムリトサル旅行後編。
2009年8月1日から3日にかけてのアムリトサル旅行。
まずは1日目の様子から。 デリーからアムリトサルに入り、黄金寺院とジャリヤーンワーラー庭園を見る。
本日、論文を1本とりあえず書きあげた。まだ修正作業はあるが、とりあえずこれで一段落。日本滞在中にやる予定で持ち越しとなっていた課題を一掃した。
JNUでは21日までの1週間が在学生の新学期登録となっていた。自分は飛行機の遅れで出遅れ、しかもICCRの小切手発送がいつもにも増して遅いというトラブルもあったが、期限の21日夕方にかろうじて手続きを終えた。このあと、JNUは新入生の登録シーズンとなるが、在学生はその間しばらく時間的猶予がある。知り合いのなかには、登録を終えて、今月末までいったん田舎に帰ってしまう人もいるほど。 ちょっと時間に余裕ができたので、今日は部屋の掃除。どうも寮の一人部屋を確保するにはもう少し時間がかかりそうで、今の部屋にもうしらばらく世話になることになりそうだ。
夏休み2ヶ月の日本滞在中に、いくつか印象に残った本との出会いがあった。その中の1冊がこれ。本屋で偶然にめぐり会えた。
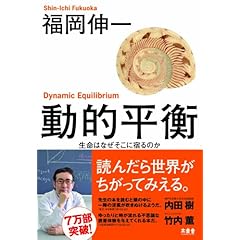 福岡伸一『動的平衡―生命はなぜそこに宿るのか』(木楽舎、2009年) 目にとまった理由は、その帯。福岡先生の写真、はどうでもいい。 「読んだら世界がちがってみえる。」 これも別にどうということのないキャッチコピーだ。ありがち。そこではなく、推薦者の言葉が気になった。 「先生の本を読むと頭の中に一陣の涼風が吹きぬけるようだ」(内田樹) 「ゆったりと時が流れる不思議な読書体験を与えてくれる本だ」(竹内薫) 科学の本に対する評としては、おかしい。気になり、手にした。ちょっと目を通すと、評者の言う意味がわかった。たしかに、そのような感じがする。涼風。ゆったりとした時。的確な評だ。スマートな文章に心を奪われた。 自分が論文を書くとき、誤解を読み手に与えないことを意識する結果、冗長な文章を書く癖がある。また、論理構成をうまく表現できずに苦しむことが多々ある。そこで、文章の教材として、この本を買うことにした。 実際に読んでみると、内容も実に興味深い。さまざまな疑問に、広く認められている学説と、著者の仮説を交えて、説得的な説明が展開される。 たとえば、なぜ大人になると時間が早く過ぎるように感じるのか、というパズルがある。本書によると、その理由は、体内時計の基礎となる新陳代謝が加齢とともに遅くなるからだという。つまり、年をとると、新陳代謝が遅くなる。すると、新陳代謝の速度に基づいている体内時計も遅くなる。時計の針がゆっくり回るようになるというイメージ。仮に体内時計が半分の速度で進むとすると、現実1年間が経過したとき、まだ半年しか経っていないと感じられる。しかし現実には1年の時が進んでいるので、時間が早く経過してしまったように感じられる。(40~45ページ) 本書のタイトルである「動的平衡」の部分は特に印象的だ。 以下、引用。 引用終わり。 身体は、流れる分子の一時の淀み。生命は、「動的な平衡」の生み出す「効果」。 もともとこれに近い生命観を持っていたので自分は受け入れられたが、他の人はどう思うだろうか。おそらく、すんなり受け入れられない人が多いだろう。でも、そんな人にこそ、この本を手に取ってもらいたいものだ。 |
プロフィール
HN:
toshi
性別:
男性
自己紹介:
2008年7月から2010年5月まで、ジャワ―ハルラール・ネルー大学留学。
最新記事
(07/24)
(07/22)
(07/19)
(07/19)
(07/18)
(07/17)
(07/16)
(07/12)
(07/12)
(07/11)
本棚
カレンダー
アーカイブ
ブログ内検索
カウンター
|



